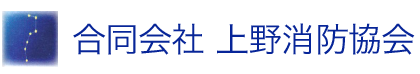事業内容
消防設備の保守・点検


火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防用設備が設置されています。これらの消防用設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。
1.点検・報告を行なう義務のある方
防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。
- 建物の所有者
- 建物の管理者:ビル管理会社や建物の管理を委託されている方など
- 占有者:テナント・建物又は部屋を借りている方など
- 管理者、占有者の義務は契約等の内容によります。
- 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 罰則・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
・その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)
2.点検・報告が必要な建物と点検実施者
防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。
- デパートやホテルなど:延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
- 工場など:延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
- その他:屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物(全体の収容人員:30人から300人)
上記以外の防火対象物(アパート等)も確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることをお奨めします。
有資格者に点検を行わせる必要のある建物
点検を要する消防用設備等の種類と必要となる点検資格
3.消防用設備の種類
防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。
- 消火器具・排煙設備
- 排煙設備
- 屋内消火栓設備
- 連結散水設備
- スプリンクラー設備
- 連結送水管(共同住宅用連結送水管)
- 水噴霧消火設備
- 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備)
- 泡消火設備
- 無線通信補助設備
- 不活性ガス消火設備
- 非常電源(非常電源専用受電設備)
- ハロゲン化物消火設備
- 非常電源(自家発電設備)
- 粉末消火設備
- 非常電源(蓄電池設備)
- 屋外消火栓設備
- 非常電源(燃料電池設備)
- 動力消防ポンプ設備
- 配線
- 自動火災報知設備
- 総合操作盤
- ガス漏れ火災警報設備
- パッケージ型消火設備
- 漏電火災警報器
- パッケージ型自動消火設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 共同住宅用スプリンクラー設備
- 非常警報器具及び設備
- 共同住宅用自動火災報知設備
- 避難器具
- 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
- 誘導灯及び誘導標識
- 特定小規模施設用自動火災報知設備
- 消防用水
- 加圧防排煙設備
4.点検の種類と点検期間
機器点検(6ヶ月に1回)
外観点検:消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
機能点検:消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
5.点検結果の報告
- 特定防火対象物 =1年に1回 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など
- 非特定防火対象物=3年に1回 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
6.点検〜報告の流れ
| STEP1 | 事前お打合せの実施 ・点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を実施致します。 |
|---|---|
| STEP2 | 点検の実施 ・機器点検:消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。 ・総合点検:消防用設備等を実際に作動させ、総合的に正常に機能するかを法令の基準に従い点検します。 |
| STEP3 | 整備の実施(不良箇所が発見された場合) ・点検において発見された不良箇所は別途お見積提出、ご相談の上、速やかに整備修繕工事を進めます。 ・整備内容は消防用設備維持台帳へ記録します。 |
| STEP4 | 点検報告書の作成 ・点検結果を設備毎に「点検票」に点検者が記載します。 ・各報告書の様式は告示で定められています。 |
| STEP5 | 点検結果報告書の提出 ・防火対象物の関係者の方は、定められた期間毎に所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。 |
防火対象物定期点検報告
防火対象物定期点検報告制度とは、消防用の設備や機材等の点検にかかわる報告制度とは別のもので、運用方法やワークフローなどの面で、建物の防火管理が正常・円滑に行われているかを点検し、報告を行う制度です。 建物の所有者や入居者などの管理権限をお持ちの方は、防火対象物点検の資格保有者に点検を依頼し、その結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。
点検報告を必要とする防火対象物
- 収容人員300人以上の特定防火対象物
- 収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物
点検の流れ
防火対象物点検の準備
防火対象物点検は書類上での確認作業も多く、以下の届け出書類を事前に準備していただく必要があります。
- 防火管理者選任(解任)届出書の写し
- 消防計画作成(変更)届出書の写し
- 統括防災管理協議事項作成及び変更の届け出の写し
- 消防用設備設置届出書
- 消防用設備等検査済証
- その他
防火対象物点検実施
防火対象物点検は原則として、防火管理者立ち会いのもと行います。
改善方法の助言
点検基準に適合していない場合は防火対象物点検資格者は防火管理者に改善のための助言をします。
点検結果報告書の作成
防火管理の改善内容等を含め、防火対象物点検資格者が点検票を作成します。
報告
管理権原者の方は消防署長等に報告書を提出します。
【点検済の表示】
表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適 合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合し ていることを情報提供するものです。
各種認証マーク
防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。
- 建物の所有者
- 建物の管理者:ビル管理会社や建物の管理を委託されている方など
- 占有者:テナント・建物又は部屋を借りている方など
- 管理者、占有者の義務は契約等の内容によります。
- 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 罰則・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
・その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)
点検・報告が必要な建物と点検実施者

-
防火基準点検済証
防火対象物点検の結果が良好であった場合は 「防火基準点検済証(防火セイフティマーク)」を1年間建物に表示する事が出来ます。 
-
自主点検報告表示制度
防火対象物点検の結果が良防火対象物点検に該当しない旅館・ホテル等の場合は点検基準に基づいて防火対象物点検資格者または防火管理者が点検を行うことにより、「防火自主点検済証」を1年間建物に表示することが出来ます。 
-
防火対象物の定期点検報告の特例認定制度
3年間連続して法令違反のない防火対象物は以後 3年間定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することが出来ます。 防火対象物の関係者が申請をし、 消防機関の検査後に認定されます。
消防法による罰則規定
「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。
防災管理定期点検報告
「防災管理」が必要となった建物では、様々な業務が義務付けられます。
防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年一回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第36条)火災だけではなく“地震”や“毒性物質事故”などの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について点検し報告する制度です。
対象建物の目安
- 11階以上・・・延べ面積10,000m2以上
- 5階以上・・・延べ面積20,000m2以上
- 4階以下・・・延べ面積50,000m2以上
- 共同住宅などの一部の建物を除きます。
1.管理権原者の義務(事業所毎)
- 防災管理者の選任
- 自衛消防組織の設置
- 防災管理定期点検結果報告書を消防署長等へ報告
2.防災管理者の主な業務
管理権原者により選任された防災管理者は主に次の業務を行います。
- 防災管理に係る消防計画の作成
1.地震時の建物や在館者の被害想定とその対策。
2.特殊な災害時の通報連絡や避難誘導と被害軽減の対策。 - 自衛消防組織の設置
防火対象物や事業所の用途、規模、収容人数等の状況に即した 防火対象物全体にわたる「防火対象物自衛消防隊」と事業所ごとの 「事業所自衛消防隊」の2つの自衛消防を組織します。 - 避難訓練の実施
消防計画をもとに年1回以上避難訓練を実施します。 - 消防計画内容の検証及びその結果に基づく計画の見直し
消防計画に沿った避難訓練や被害想定に応じた訓練を行い、 訓練の結果を踏まえた継続的な消防計画の見直しや検証を行います。 - 被害の想定及び対策
地震時の被害想定や被害対策を行います。 特殊な災害時(大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等)の通報連絡や避難誘導を行います。 - 自衛消防組織が行う活動内容
地震、その他の災害に対し、それぞれ消防機関への通報、消火活動、避難誘導、救助、応急救護等を行います。
3.定期点検までに準備して頂く書類
- 防災管理再講習の修了証の写し
- 防災管理に係る消防計画の届出に関する書類の写し
- 防災管理者選任(解任)届出書の写し
- 共同防災管理協議事項届出書の写し
- 自衛消防組織設置(変更)届出書の写し
- 防災管理定期点検結果報告書の写し
- 防災管理定期点検報告特例認定申請書の写し
- 管理権原者変更届出書の写し
- 防災管理に係る消防計画に基づき実施される事項の状況を記載した書類 等
4.必要な資格(講習)
| 業務担当者 | 必要な資格(講習) | 取得方法 | |
|---|---|---|---|
| 他講習修了の有無 | 取得の為の講習 | ||
| 防災管理者 | 防災管理講習 | 甲種防火管理講習を受けたことがない方 | 防火・防災管理新規講習 |
| 甲種防火管理講習修了者 | 防災管理新規講習 | ||
| 統括管理者 本部隊の班長 |
自衛消防業務講習 | 防災センター要員講習を受けたことがない方 | 自衛消防業務新規講習 |
| 防災センター要員受講修了者 | 自衛消防業務追加講習 | ||
- 防災管理者又は総括管理者として必要な学識経験を有する方は、講習を受講しなくとも防災管理者又は統括管理者・本部隊の班長の資格を有します。
- 資格を取得後、5年以内ごとに再講習を受講する必要があります。
5.防災管理点検資格者の点検業務
- 「管理権原者の業務(管理者の選任等、自衛消防組織の設置、点検報告)」、「防災管理者の業務」に係る全ての内容について、適切に行われているかを点検します。
- 書類審査、建物点検及び管理権原者、統括管理者、防災管理者の方々と面接をおこないます。
6.点検済証の表示
適切な運用・管理が確認されると安全・安心な建物として点検済証を表示できます。
- 注:防火対象物点検と防災管理点検の両方が対象となっている建物は、いずれか一方でも点検基準が満たされていないと「防火・防災点検済証」の表示ができません。
耐圧性能点検報告
耐圧性能点検とは
設置後一定期間を経過した「連結送水管」「屋内外消火栓等消防用ホース」はその機能に支障が無いかを確認し、消防署長等へ報告する事が消防法で義務付けられています。
1.対象および点検時期
建物の用途や大きさに関わらず設置後10年以上経過した「連結送水管」「屋内外消火栓等消防用ホース」が点検の対象となります。その後は3年毎に点検と報告が必要です。
2.連結送水管耐圧性能試験方法(湿式配管)
送水口から動力消防ポンプなどの試験機器を用いて送水・加圧した後、一定圧を3分間保持した状態で送水口本体・配管・接続部分・弁類の変形、漏水などがないことを確認します。
取扱い製品例
| 消火器 | モリタ、ミヤタ、その他 主要メーカー |
|---|---|
| 感知器 | ニッタン、その他 主要メーカー |
| その他 | ニッタン、その他 主要メーカー |